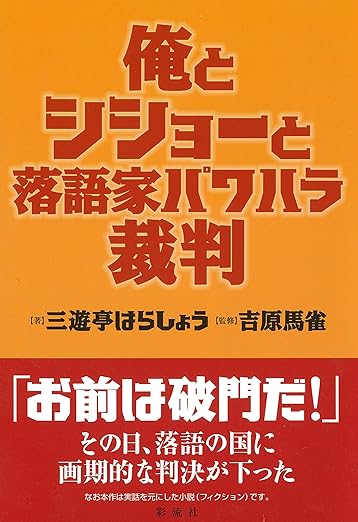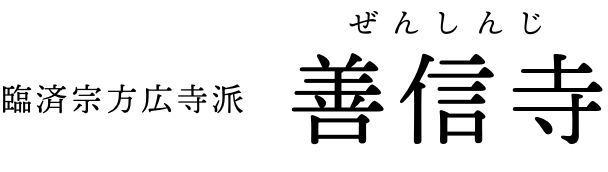私は落語が好きなので、落語界周辺の本にも興味があり、購入履歴からのアマゾンのお勧めで今回この『俺とシショーと落語家パワハラ裁判』という本を知り、購入し、一気に読みました。
落語の世界に限らずですが、特に古典芸能の世界は弟子が師匠に入門すれば、その師匠は絶対的存在であり、いわゆる「上の者が白いと言えばカラスも白い」という世界のようです。決して論理的とは言えないような教育方法の中で「修行」が進み、その中で能力や知識を体得していくわけです。もちろん古典芸能だけでなく、他にも相撲界とか軍隊的な組織、あるいはやくざなどもそういった性格を持つ社会のようであり、そしてまた私のいる社会である禅宗寺院も似通った性格があるのではとも思えます。禅宗の修行というものも、ある種、理不尽なのではと思えてしまうような体験もいたします。
この本は、その社会の在り方はある程度理解の上で入門したものの、「入門者にも最低限の人権はあります」という主張の下、師匠を訴えるという内容の本で、私もいろいろと考えさせられる内容でした。
昨今は寺院の後継者不足という問題が徐々に重要視されてきております。そんな中、願書と履歴書を提出すればすぐに僧侶の資格が取れるような宗派とは違い、禅宗はどこも禅の修行の実体験を重んじ、決して短くはない年月、修行生活に入ることを求められます。その過程では、昔ももちろんでしょうし、昭和の終わり頃の私のときもあったことですが、修行に嫌気がさして逃げてしまう者もおりました。しかしそれはいたとしても少数であり、長い短いはそれぞれとしても、それなりの年月を全うし資格を得て去る者がほとんどでした。それがいまや、修行に出て資格を得て去る者が少数派であるかのようにも感じられ、実に多くの者が逃げてしまうという事実があるようです。方広寺でも、管長猊下が宗誌で嘆かれるほど多くの者が挫折し、山を降りております。
務まらなかった者はしょうがない、という考えもわかるのですが、ここから先、修行道場での体験を理不尽に思い、訴えるという者が出てきはしないかということが、私が危惧するところです。
この『俺とシショー~』で訴えられた師匠は、確かに理不尽な振る舞いで、弟子の人権をあまりに軽視しており、訴えられることもやむなしと思えました。ですが禅宗の修行には、一見理不尽に思えても、そこには会得すべき先人の確固たる思想があり、また入門者の一日も早い僧堂への適応と修行の全うのための愛情もあると、私は思っています。そしていじめはありません。少なくとも私は経験していません。私が修行した天龍寺僧堂以外の僧堂でも同様と思いたいです。そう思える修行生活を送ることができた私は、苦しくつらかったのは事実としても、やはり幸せでした。でもそう思えなかった者が、本山を、老大師を、諸先輩方を訴えるというようなことになれば、禅宗も終わってしまうかもしれない、そんなことを考えながら、読了いたしました。
修行とパワハラ